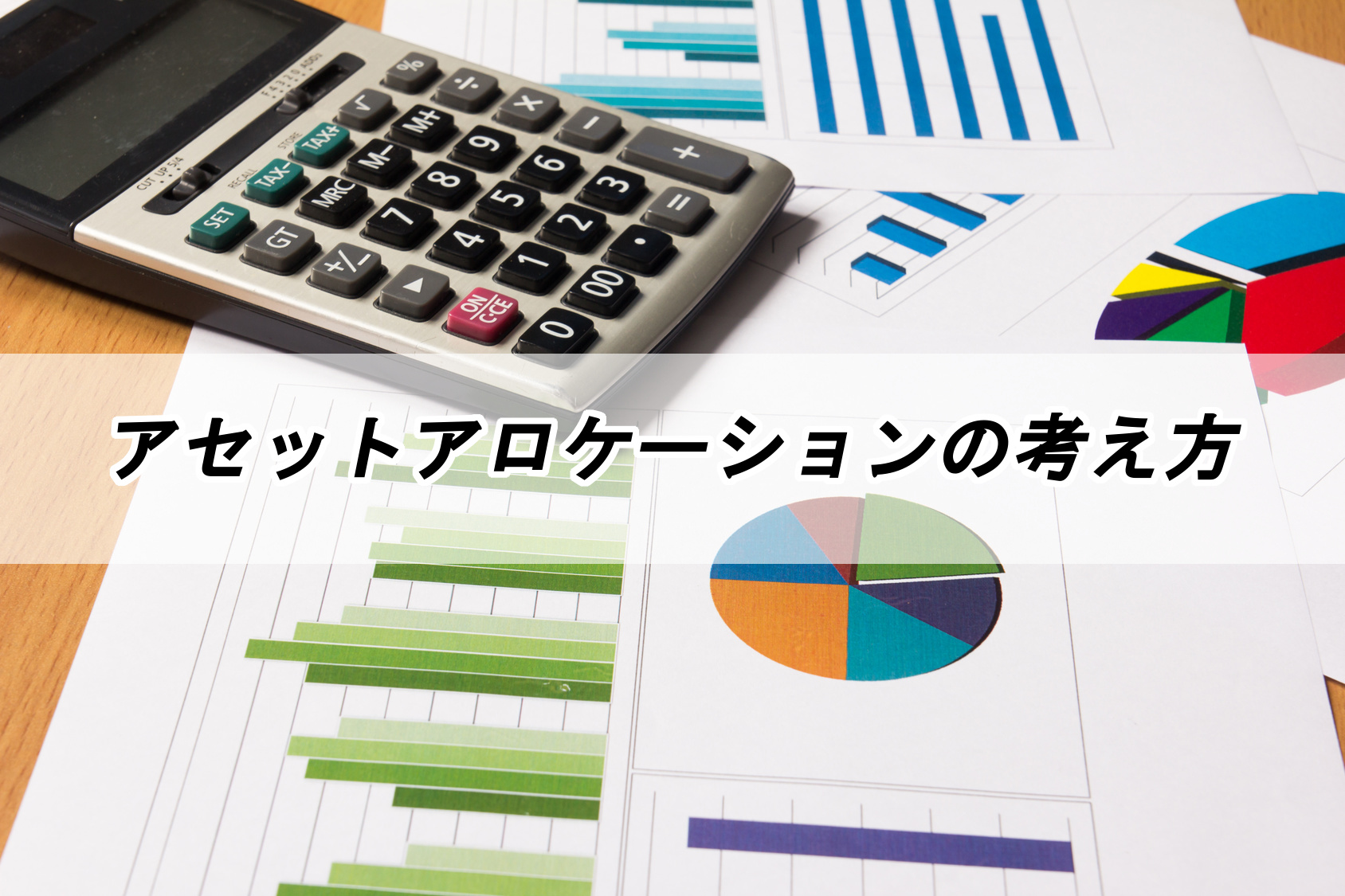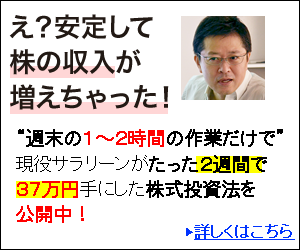絶対読んで欲しい編集部おすすめ記事4選!
iDeCoは、将来もらえる年金額が運用の成果次第で変わる「自己責任の原則」に基づく制度です。
つまり、年金を増やすも減らすも自分次第。
少しでも多く年金がもらえるように上手に掛金を運用しなければなりませんが、そこで知っておかなければならないのが「アセットアロケーション」です。
これまで資産運用を積極的に行ってこなかった方には難しく感じるかもしれませんが、言葉の意味から実際の運用まで、順を追ってわかりやすく解説します。
>>【無料】ゼロから安定して稼ぎ続ける投資家育成講座をタダで学ぶ目次
アセットアロケーションとは
iDeCoにおけるアセットアロケーションとは、積み立てる掛金の投資割合を決めることです。
アセットアロケーションの言葉の意味
「アセット」と「アロケーション」に分けて考えましょう。
iDeCoのアセットとは、月々積み立てる掛金のことです。
月額は少なくてもiDeCoでは長期間継続して積み立てることになりますので、合算すると大きな金額になります。
iDeCoのアロケーションとは、積み立てた掛金を複数の運用商品に配分することです。
つまり、掛金の投資割合を決めることとなります。
どうやってアセットアロケーションするか?
加入したiDeCoの運用管理機関が、世の中にたくさんある金融機関の、たくさんある金融商品の中から選んで、加入者に提示します。
加入者は、その中から複数の商品にパーセンテージまたは金額を指定して掛金を振り分けます。
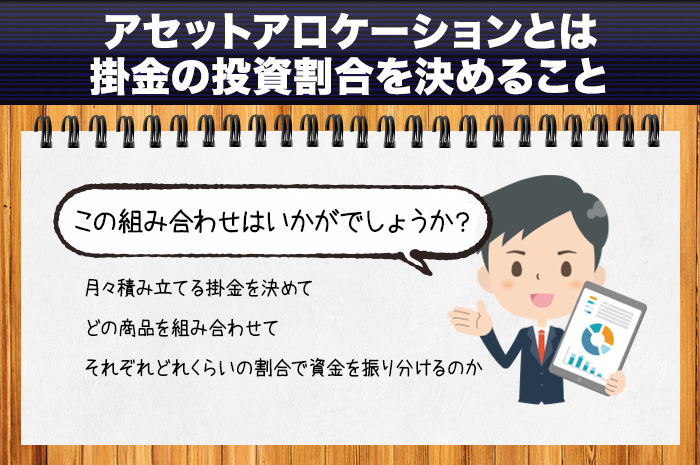
例えば、運用商品Aに40%とBに60%投資します。
ひとつの運用商品への投資割合を100%にすることも可能ではありますが、それは賢い運用とは言えません。
すべての掛金を振り向けた運用商品が将来値下がりすれば、私たちが老後に受け取る年金額が減ってしまうことに直結するからです。
そこで、掛金を振り向ける運用商品を複数に分散させることで、年金額が減ってしまう事態を回避し、安定した資産形成を目指せるのです。
運用商品の種類
運用商品には「元本確保型」と「価格変動型」があります。
運用管理機関から渡される資料には、運用商品がどちらなのかが明記されています。
元本確保型には銀行預金が採用されることがほとんどです。
銀行預金は預金保険制度の対象となっており、お金を預けた銀行がつぶれても、預金者一人あたり元金1,000万円とその利息は戻ってくるので、iDeCoの掛金もほぼ確実に元本が保証されます。
価格変動型は、掛金が増えることもあれば、減ることもあります。
その多くは「投資信託」で、投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、お金の運用の専門家が株式や債券などに投資、運用する商品です。
その運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配される仕組みです。
運用管理機関に運用方法をきいてみよう
運用管理機関が、運用商品について紹介した冊子やネット上に詳しい説明を用意しています。
難しいと感じられる方は運用管理機関に教えてもらいましょう。
運用管理機関には、加入者がアセットアロケーションをしやすくなるよう「継続投資教育」を行う努力義務が課されています。
そのため、iDeCo専用のコールセンターを設けている運用管理機関が多いです。
そのうえでHPやパンフレットに掲載された詳しい説明を読むとよく理解できるようになります。
アセットアロケーションは変えられる
経済状況の変化に応じて資産配分を変更できます。
既にある運用商品で積み立てた資産を、別の運用商品に移し替えることもできます。
例えば、
「これまですべての掛金を元本確保型の定期預金で運用していたけれど、これから国内景気が上向いて日本株が値上がりしそうだから、積立てる掛金の半分を日本株投資信託に振り向けよう。」
「来年は円高になりそうだから、これまで外国債券の投資信託で運用していた掛金の半分を国内債券の投資信託に移そう。」
といったことが可能となります。
- アセットアロケーションとは積み立てる掛金の投資割合を決めることで、経済状況の変化に応じて変更することができる
リスク許容範囲を考えよう
運用商品を選ぶにあたっての前提になるのが、加入者ひとりひとりのリスク許容範囲です。
期待リターンと元本割れリスク
iDeCoのアセットアロケーションにおいて「リターン」とは、運用商品から生み出される利息や分配金、値上がり益のことです。
価格変動型の運用商品を選ぶときには値上がりを「期待」します。
「リスク」とは、iDeCoの投資割合を決める際に期待したリターンどおりにならないことです。
例えば、
「来年は円安になりそうだから掛金の多くを外国株式投信に振り向けたものの、実際には円高に振れ、世界的な景気悪化で株価が安くなったために、その外国株式投信が値下がりした。」
このように、元本を割り込む可能性もあります。
誰しも損するのは嫌ですし、ましてやiDeCoでは私たちの大切な老後資金を積み立てているわけですから、リスクは負いたくはありません。
リスクを負わずにリターンは得られない
今の低金利はこの先しばらく続くことが確実視されていますので、損したくないからと言って、元本確保型の運用商品にばかり掛金を振り向けていると、老後に受け取る年金額を増やすことはできません。
年金額を増やすためには、ある程度のリスクを負わなければならないのです。
iDeCoの資産配分を決めるにあたっては、リスクとリターンは両立しないということを念頭に置いておく必要があります。
どこまでリスクを負っていいと考えるかの許容範囲は、持ち家の有無、親からの遺産相続の有無、現在と将来の収入などによって人それぞれです。
個人の人生観にもよります。
▼おすすめ記事
【iDeCoを始める前に注意点を把握しよう】
- iDeCoのアセットアロケーションにおいてリスクを負わずにリターンは得られない
- リスク許容範囲をふまえたうえで運用商品を選ぶ必要がある
スポンサードサーチ
理想のアセットアロケーション
加入者のリスク許容範囲によって理想のアセットアロケーションは異なってきますが、いくつか例をご紹介します。
資金的に余裕がある方
金融資産があって、株などの資産運用に慣れていらっしゃる方は、iDeCoでリスクを取ることができます。
つまり、掛金を元本変動型、特にリスクが高く値上がり益を狙える投資信託に振り向けるということです。
iDeCoでの投資信託購入は、一定額を定期的に購入します。
運用商品の投資信託の価格は常に変動しますが、価格の変動に関係なく、定期的に一定額を買い付けていくため、価格が安い時には多く買い、価格が高い時には少しだけ買うことになります。
高い時にも安い時にも継続的に買い続けることで、購入単価をならしていく、つまりは、低くする効果が期待できるのです。
その分、収益を大きくできて、さらにその収益は非課税となります。
損するのが絶対イヤな方
リスクを取りたくない方は、元本確保型一本やりで行くしかありません。
資産運用に興味がない、お金のことを考えるのが嫌い、そんな時間はないという方も同様です。
年金額を増やすことはできませんが、高インフレの時代にならない限り、お金が目減りすることはなく、節税メリットだけを受け続けられます。
iDeCoで運用する期間が短い方
短期の運用であれば、元本変動型は避けたほうがよいでしょう。
なぜなら、リーマンショックのような大きな経済ショックがあって、運用していた元本変動型の投資信託が値下がりした場合、元に戻るのに相応の時間を要することがあるからです。
▼おすすめ記事
【iDeCoへの加入資格は?3つの条件をチェックしよう】
- 資金的に余裕がある方は積極的にリスクを取った運用
- 損するのが絶対イヤな方は元本確保型一本やり
- 運用する期間が短い方は元本変動型を避ける
iDeCoの運用はSBI証券がおすすめ!
iDeCoを取り扱う運用管理機関を選ぶにあたり、以下2つのポイントが重要になります。
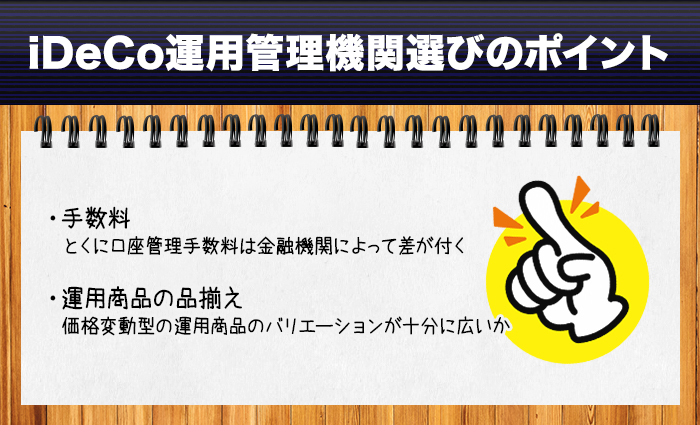
特に価格変動型の運用商品のバリエーションが十分に広いか、ということは重要です。
年金をもらう60歳までの間にはブラックマンデーやリーマンショックのような大きな変動があるかもしれません。
老後のための大切な資産ですから、そんな時でも減らさないようにしておかなければなりません。
そのためには、値動きが異なる複数の運用商品に掛金を分けておく必要があります。
なぜなら、仮にその中のどれかが値下がりしても他の運用商品の値上がりで、全体では大きく減らないようにできるからです。
この点で最多の運用商品を揃えているSBI証券はお薦めです。
手数料が安いのも魅力となります。
- アセットアロケーションの選択肢が最多で手数料も安いSBI証券はお薦め
スポンサードサーチ
まとめ
iDeCoで年金額を増やすために最重要となる「アセットアロケーション」。
わたしたち加入者ひとりひとりのリクス許容度によって、さまざまなアセットアロケーションができます。
この記事が、みなさんのベストなアセットアロケーションを行う一助になれば幸いです。
絶対読んで欲しいおすすめ記事!
いいね!しよう
情報を受け取れます