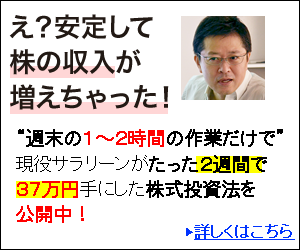絶対読んで欲しい編集部おすすめ記事4選!
投資信託を使っている人は、レーティングも大変気になると思います。
なかでも5つ星のファンドは安全で儲かりそうな気がしますから、投資してみたくなりますよね。
しかし、レーティングは投資信託の1つの指標に過ぎませんから、過信すると大きなリスクを抱えるなどの不利益を受ける恐れも。
一方、レーティングをうまく使うことでより高いリターン、あるいはよりリスクの低いファンドを選んで投資することが可能です。
今回は、レーティングの示す意味や内容とその限界、及び上手な活用法について解説します。
>>【無料】ゼロから安定して稼ぎ続ける投資家育成講座をタダで学ぶレーティングとは
レーティングの詳細について触れる前に、その意味について解説していきます。
投資信託の格付けを示す
レーティングとは、投資信託の格付けのことです。
投資信託の格付けが高いということは、低いリスクで高い収益をあげているファンドということを示します。
投資先が類似するファンドどうしで比較した場合、同じリスクならばより高い収益を、収益が同じならばよりリスクが低いファンドの方が、高いレーティングを獲得することになります。
主に使われるものはモーニングスターのレーティング
投資信託の格付けを行っている会社は、モーニングスターやイボットソンなど、複数あります。
その中でも最も多く使われている格付けは、モーニングスターが行う「スターレーティング」でしょう。
本記事では、モーニングスターのレーティングを中心に解説していきます。
▼おすすめ記事
【投資信託の仕組みや基礎知識を解説します】
- レーティングとは投資信託の格付けを示すもの
- モーニングスターのレーティングが投資家の代表的な指標となっている
レーティングが示す内容と誤解しないためのポイント
レーティングは投資信託の指標の1つですが、万能ではありません。
ここではレーティングが示す内容と誤解しないためのポイントを解説します。
リターンは高く、リスクが低いほど評価は高い
レーティングにおいては、リターンはより高く、リスクはより低いファンドほど高い評価を受けることができます。

出典:これさえ覚えれば投信選びも簡単!?「投資信託」の上手な探し方!
詳しい算出方法は、「レーティングの決め方」にて解説します。
「レーティングが高い=安全」ではない
投資信託のレーティングが高いことは、投資先が類似するファンドどうしで比べたとき、よりリターンが高かったり、リスクがより低いということを示すものです。
従って、レーティングが高いからといって安全で高い収益が望めるとは限りません。
例えば、投資信託のなかには「ハイイールド債」という債券を主な投資先とするファンドがあります。
ハイイールド債は、長期格付けで「投資不適格」や「投機的格付け」とされる社債などを指しており、発行する企業の信用が低いため、投資家に投資をしてもらえるように利率を高くしています。
そのため、レーティングが高いファンドも出てくるかもしれません。
しかし、ハイイールド債そのものがリスクの高い金融商品ですから、ハイイールド債を主な投資先とするファンドどうしで比べても、安全性が高いファンドは見つけられません。
レーティングは過去の実績であり、将来は予想しない
レーティングを見る際には、もう1点注意しておきたい点があります。
レーティングは過去の実績を示すものであり、将来の予想ではないということです。
従って、未知の事態が発生した場合は、レーティングがまったく参考とならない可能性もあります。
もっとも通常の場合、景気は良いときと悪いときを循環するものです。
2018年時点であれば、10年以上運用されているファンドなら好景気・不景気両方の時代を経験しています。
従って高いレーティングを長期間継続できているファンドは、環境の変化があっても、よりよい成績を上げ続けられるファンドと言えます。
評価の高いファンドは運用期間にも注意が必要
評価の高いファンドであっても、運用期間が短い場合は注意が必要です。
さきに解説した通り、レーティングは過去の実績を示したものに過ぎません。
そのため運用期間の短いファンドであるほど、市場の大きな下落にさらされていない可能性は高くなります。
運用期間の短いファンドが2009年のリーマンショックのような事態に直面した際、どのようになるかは誰にもわかりません。
評価の高いファンドであっても運用期間が短い商品に投資する場合は、市場環境によっては想定しない事態が起こり得る点にも注意が必要です。
▼おすすめ記事
【投資信託のリスクとは?チェック方法と対策について解説】
- レーティングは類似のファンドと比べて、リターンが高い、またはリスクが低い運用成績であったことを示している
スポンサードサーチ
レーティングの決め方
モーニングスターではレーティングの決め方を開示していますので、このルールについて解説します。
3年、5年、10年の期間ごとに、星の数は変わる
モーニングスターでは、3年、5年、10年のそれぞれについて、レーティングを算出しています。
レーティングの値は、以下の方法で算出されています。
①まず、それぞれのファンドごとにリターンとリスクを算出します。
この数値は、どちらもモーニングスター独自の基準で算出するものです。
②次にリターンからリスクの差を算出します。
各ファンドのそれぞれの値を計算した後、モーニングスターが定めた小分類ごとに順位をつけます。
③その後、星の数を以下に示す割合で各ファンドに割り当てます。
| 星の数 | 順位 |
| 5個 | 上位10%まで |
| 4個 | 上位10%超、32.5%までの範囲内 |
| 3個 | 上位32.5%超、67.5%までの範囲内 |
| 2個 | 上位67.5%超、90%までの範囲内 |
| 1個 | 上位90%超(下位10%未満) |
従って同じファンドでも、3年と5年の星の数は異なることがあります。
総合レーティングの決め方
総合レーティングの決め方は、ファンドが発売開始されてからどれだけ経過しているか、つまり運用期間によって変わります。
具体的には、3年、5年、10年の各レーティングの数値を、以下の割合で合算した数値となります。
但し運用期間が5年に満たないファンドは、3年レーティングの数値と同一となります。
| 運用期間 | 3年レーティング | 5年レーティング | 10年レーティング |
| 3年以上5年未満 | 100% | 無し | 無し |
| 5年以上10年未満 | 40% | 60% | 無し |
| 10年以上 | 20% | 30% | 50% |
なお詳しいレーティングの計算方法は、モーニングスターの「総合レーティング」をご参照下さい。
- レーティングには3年、5年、10年及び総合レーティングがある
レーティングは商品選びの目安の1つ
レーティングは投資信託の商品を選ぶ上で便利な指標ですが、1つの目安でしかありませんから、運用成績や手数料などもあわせてチェックすることが重要です。
異なる種類の投資信託のレーティングを比較することは無意味
レーティングの算出は、モーニングスターが定めた小分類ごとに分けて行われます。
この小分類は79項目もあります。
従って、株式型と債券型、REIT型といった投資信託どうしを比較することはもちろん、以下のような比較も小分類が異なりますから無意味です。
- 国内株式型について、大型株と小型株の投資信託を比較する
- 国内債券型について、短期債(1年未満の債券が中心)と中長期債(1年以上の債券が中心)を比較する
- 国際株式型について、中国に投資する投資信託と、アメリカに投資する投資信託を比較する
無理やり異なる小分類のレーティングを比較すると判断を誤り、リスクの高い、あるいはリターンの低いファンドに投資するおそれがありますから、注意が必要です。
運用成績や手数料などのチェックも必要
レーティングは投資信託の運用成績をわかりやすく示す指標の1つですが、ここまで解説してきた通り万能ではありません。
レーティングだけで投資先を決めるのではなく、投資先の選定方法の1つとして使うことがおすすめです。
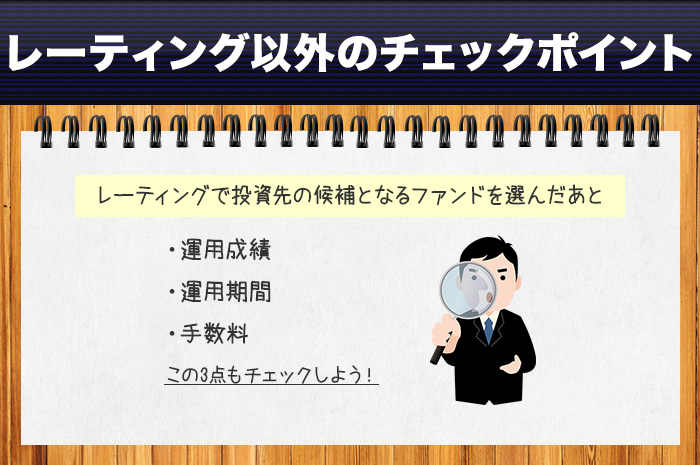
最初からレーティングを参考にして決めるのではなく、国内債券に投資したいので具体的なファンドを選びたいという段階になってから、レーティングを参考にすると良いでしょう。
レーティングで投資先の候補となるファンドを選んだあとは、運用成績や運用期間、手数料などもチェックして、あなたが納得できるファンドに投資することが大切です。
▼おすすめ記事
【良い投資信託選びをするためのアセットアロケーションの考え方とは】
- 投資信託の商品選びはレーティングだけに頼らず、運用成績や手数料などもチェックすることが重要!
スポンサードサーチ
まとめ
レーティングはファンド選びに役立つ指標の1つですが、あくまでも類似のファンドどうしを比較する手段として用いられるものです。
投資先を国内債券にするのが良いか、外国株式が良いかといった方向性は、レーティングではわかりません。
これらは、レーティングを見る前に決めておくべきものです。
その後の、具体的な商品選びの際には、レーティングがよりリターンの高く、リスクの低い商品を選ぶ手助けとなります。
もっともレーティングだけでなく、他の項目もチェックした上で、投資するファンドを決めることが大切です。
投資信託はあくまでも自己責任であることを忘れないようにしましょう。
絶対読んで欲しいおすすめ記事!
いいね!しよう
情報を受け取れます